
全固体電池は実用化できないできないのでしょうか。全固体電池のデメリットふまえたBMW社としてのスタンスを解説します。
全固体電池のメリット・デメリット
全固体電池のメリット
- 固体による燃えるリスクを大幅軽減、安全性に寄与
- 充電時間の短縮
- 固体による体積の集約、極小化(大容量化に繋がる)
- 固体による発熱の減少が見込まれる
- 耐久性に優れ、高寿命とされる
全固体電池のデメリット
- 電極と電解質を常に密着させる必要があり、固体と固体を常に密着させることが難しい
- 最適な材料の選択が難し
- 固体電解質のイオン伝導度の低い(液体電池に劣る)
- 固体の冷却に液体が欠かせない(エンジンを水冷で冷やしているのと同じ)
- 製造コストが高い
- まだ開発途上である
- 計画した耐久性に達しておらず、寿命が短い。
スマホやPC用のリチウムイオンバッテリーが、圧倒的なシェアに比べて、全固体電池は細々と市場に投入されている段階であり、製品としての競争力はゼロに等しいです。
全固体電池は実用化できない
全固体電池は実用化されたとのニュースが度々登場します。しかし、製造コストや耐久性など、数々の問題点を抱えており、いまだに完全な全固体電池としての実用化が達成できない状況です。
実用化できない問題点
電池寿命が短い
- 繰り返し充放電による性能が低下。寿命が短い
- 固体化しているものの、落下などの衝撃に弱い
製造コストが高く既存バッテリーに対して全く競争力がない
- 全固体用の製造設備を導入する、開発費用と初期投資の費用が莫大
- 長年、開発研究を行うものの、計画した性能に達していない
- コスト削減以前の性能的な問題が多い(液体電池に比べて、固体化に伴う様々な問題が未だに完全解決できていない)
実用化出来ない4つの課題
全固体電池(All-Solid-State Battery, ASSB)は、次世代電池としてリチウムイオン電池を超える性能が期待されていますが、まだ実用化にはいくつかの課題があります。特に以下の4つが大きな壁とされています。
1. 固体電解質の導電率不足
全固体電池では、従来の液体電解質の代わりに固体電解質を用います。しかし、多くの固体電解質はイオン伝導率が液体に比べて低く、電池の出力や充電速度が制限されます。
特に低温下でのイオン移動が遅く、寒冷地では性能低下が顕著になる問題があります。
2. 電極との界面抵抗
固体電解質と電極(正極・負極)の接触面で、イオンの移動がスムーズに行かず「界面抵抗」が発生します。この抵抗は電池の充放電効率や寿命に直接影響します。
長期使用で微小な空隙や反応層が生じ、性能低下の原因。
3. 製造コスト・量産技術の難しさ
全固体電池は高純度材料の使用や精密な積層プロセスが必要で、従来のリチウムイオン電池より製造コストが高くなります。また、薄膜化や大容量化に対応した量産技術がまだ確立されていません。
大量生産やコストダウンが課題で、自動車や家電への広範な普及が難しい状況です。
4. 安定性・寿命の問題
固体電解質は液体と比べて化学的に安定ですが、充放電サイクルで電極と反応して微細な破壊やデンドライト形成(リチウムの樹枝状成長)が起こることがあります。
特にリチウム金属負極を使う場合、短絡や発火リスクがゼロではないため、安全性の確保が課題です。
全固体電池はゲームチェンジャーなのか
全固体電池実用化のニュースが一斉に流れた2023年
トヨタ発表の2027-28年とされ、ホンダ・日産も追従するニュースが流れ、経済産業省も支援する流れのメディア報道です。
あたかも、日本メーカーがBEV出遅れを巻き返し、日本勝利のゲームチェンジャー説がメディアやSNSを駆け抜ける状況でした。
BEV低迷のニュースが流れると一斉にトーンダウン
VWのリストラやメルセデス、ボルボのBEV計画見直しのニュースが流れると、国内メディアの全固体電池のニュースは一斉にトーンダウンしました。
ここぞとばかりにトヨタも計画延長を発表しています。
まずは市販化したという既成事実の目的が優先
国内メーカーにとって、全固体電池の市販化に漕ぎ着けたというロードマップが優先され、日本製BEVのシェア獲得という、本来の目的は未達の状況です。
今の時点では、全固体電池が日本のBEV競争力をアップさせるという「ゲームチェンジャー論」として、達成は無謀という状況が理解できると思います。
BMWは全固体電池よりも既存技術を重視
BMWの次世代電池技術担当副社長マーティン・シュスター氏
2025/2:AUTOCAR JAPANより引用
BMWグループのEVラインナップに全固体電池が必要になるまでには、まだ8年はかかるだろうと予測している。 同氏は次のように述べた。
「最も重要なのは(液体)リチウムイオンバッテリーだ。まだ完成しておらず、改善の余地がある。唯一無二の電池というものは存在せず、実現しない。
しかし、リチウムイオンバッテリーはコスト削減という主要かつ最も重要な目標の達成に向けて、着実に改善できる」
「今、(全固体電池を)作ることもできるが、パッケージングにかかるコストを考えると、やる意味はない。リチウムイオンにはまだ長い道のりがある」
BMWは、2024年のBEV販売実績として、老舗エンジンメーカーとしてもベスト10に入る販売実績を残しており、BEVとICEの共用ボディなど、堅実な販売実績に繋がっています。
トヨタとの提携により、トヨタ製THS2をBMWに取り込むこともせず、トヨタ製FCEVの市販化も試作車に留めるなど、今後の電動化とBMWグループのとしての最適が技術は何か、絶えず模索している点が理解できるでしょう。
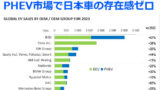


BMWの取り組み

他メーカーの追い上げで日本は家電の二の舞か
- メルセデス・ベンツ、ステランティスグループ、ヒョンデ・キアグループ:「ファクトリアル・エナジー(Factorial Energy)」
- フォルクスワーゲングループ:「クアンタムスケープ (Quantum Scape)」
試験走行車両など、公開車両については日本を凌駕し、先行する部分も目立ってきており、このままでは、海外メーカーに先を越される可能性も高まっています。
よくある質問(FAQ)|全固体電池とBMWのスタンス
Q1. 全固体電池は本当に「実用化できない」技術なのですか?
いいえ、全固体電池は「実用化できない」技術ではありません。ただし、現時点では量産・コスト・耐久性の面で大きな課題が残っているため、リチウムイオン電池のように広く普及する段階には至っていません。特に自動車用途では、充放電サイクル寿命、急速充電時の安定性、製造歩留まりといった点がボトルネックとなっています。
Q2. なぜ全固体電池はこれほど実用化が難しいと言われるのですか?
最大の理由は、固体電解質特有の課題にあります。液体電解質と比べてイオン伝導率の確保が難しく、電極界面での抵抗増大やクラック(微細な割れ)発生などが問題になります。また、高精度な製造プロセスが必要となり、現行のリチウムイオン電池工場をそのまま流用できない点も、実用化を遅らせる要因です。
Q3. BMWは全固体電池の開発を諦めているのでしょうか?
BMWは全固体電池を否定しているわけではありません。むしろ、「長期的に有望な技術」と位置付けつつ、短期的な主力には据えていないというスタンスです。BMWはパートナー企業と共同で全固体電池の研究開発を継続していますが、当面は改良型リチウムイオン電池の進化を優先しています。
Q4. BMWが全固体電池に慎重な姿勢を取る理由は何ですか?
BMWは「技術的な完成度」と「顧客に提供できる信頼性」を重視するメーカーです。全固体電池は理論上の性能は魅力的である一方、実使用環境での耐久性や長期品質の検証が不十分です。そのため、未成熟な技術を先行投入してブランド価値を損なうリスクを避けていると考えられます。
Q5. BMWはなぜリチウムイオン電池の改良を重視しているのですか?
現在のリチウムイオン電池は、エネルギー密度、安全性、コストのバランスが非常に高いレベルにあります。BMWはセル化学の改良や円筒セルの採用、熱管理技術の進化によって、現行技術でも十分な航続距離と実用性が確保できると判断しています。これにより、全固体電池を待たずとも競争力のあるEVを提供できます。
Q6. 全固体電池が実用化された場合、BMWのEVは大きく変わりますか?
仮に全固体電池が量産レベルで実用化されれば、航続距離の延長、充電時間の短縮、バッテリーパックの小型・軽量化が期待できます。ただしBMWは、「技術が成熟した段階で柔軟に採用する」姿勢を取っており、全固体電池の登場が即BMWのEV戦略を根本から変えるとは限りません。
Q7. BMWの全固体電池搭載EVはいつ頃登場すると考えられますか?
現時点では、BMWが市販車に全固体電池を本格採用する明確な時期は示されていません。業界全体では2030年前後が一つの目安とされていますが、BMWは「時期ありき」ではなく、性能・耐久・コストの全てが基準を満たした段階で導入する方針です。
Q8. 全固体電池が普及しなくても、BMWのEV戦略に問題はありませんか?
大きな問題はありません。BMWはマルチパス戦略を採用しており、EVだけでなくPHEVや内燃機関の高効率化も並行して進めています。そのため、全固体電池の実用化が遅れても、現行電池技術の進化によって十分に競争力を維持できると考えられています。
Q9. 全固体電池は「夢の電池」として誇張されすぎていませんか?
メディアでは全固体電池が「一気にEVの欠点を解消する技術」として語られることがありますが、実際には段階的な進化の一つに過ぎません。BMWのスタンスは現実的で、過度な期待を煽らず、実証された技術のみを商品化するという姿勢が読み取れます。
Q10. 消費者は全固体電池の登場を待つべきでしょうか?
多くのユーザーにとって、全固体電池を待つ必要はありません。現在のBMW製EVでも日常利用や長距離走行に十分な性能を備えています。全固体電池は将来的な選択肢として注目すべきですが、「今買えるEVが未完成」というわけではない点を理解することが重要です。
全固体電池は実用化できないのか、BMWのスタンスまとめ
- 全固体電池の実用化は、8年後の2033年以降
- 全固体電池は、未だに完成していない
- 既存のリチウムイオンバッテリーのコストや性能に改善の余地がまだまだある
- 既存の液体バッテリーの低価格化スピードに追い付けない
- 全固体電池がゲームチェンジャー化するには時間が掛かる
BMW社としては、現時点では全固体電池の実用化は難しいという結論になっています。
BMWのスタンスは、老舗エンジンメーカーとして、次世代技術の動向を見据えた堅実な経営を行っている判断される「まとめ」になります。




コメント